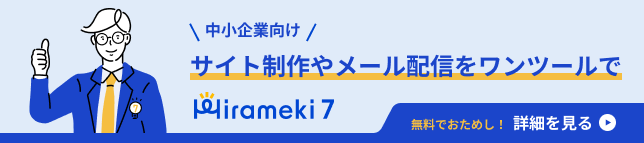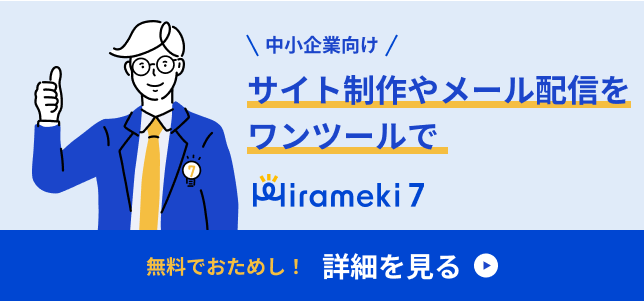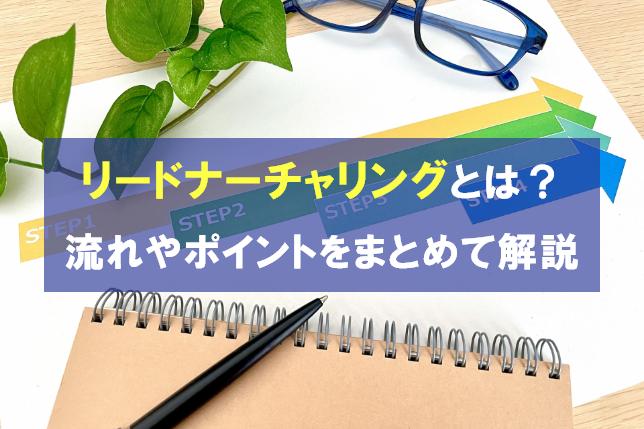新しい顧客を獲得したい、営業活動やマーケティング活動の効率を高めたいと考える企業にとって、「リードクオリフィケーション」は重要なポイントです。リードの中から今すぐ商談につながる可能性が高い人を抽出し、優先順位をつけることで、限られたリソースを最も効果的に活用できます。
本記事では、リードクオリフィケーションの手順やポイントなどをわかりやすく解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
リードクオリフィケーションとは?
リードクオリフィケーションは、獲得したリード(見込み顧客)から、購入や契約につながる見込み度合いの高い顧客を抽出する活動です。この活動ではリードがどの段階にあるのかを判断し、次のアプローチすべきターゲットを明確にします。一般的にはリードナーチャリング(見込み顧客の育成)でさまざまな施策を行い、その反応や行動ごとに得点(スコアリング)を付与します。このスコアの合計が高い顧客ほど購買に近いため、営業やセールス部門が優先的にアプローチするのが一般的な流れです。
BtoB(企業間取引)ではBtoC(一般消費者向け)よりも購入までに時間がかかり、多くの関係者の承認も必要です。そのため、段階的にリードジェネレーション(見込み顧客獲得)の活動を行い、さらにリードナーチャリングを経て、最終的にリードクオリフィケーションへと進みます。
例えば、資料ダウンロードやセミナー参加、ホワイトペーパー入手などWebサイトの行動ログを点数化し、合計ポイントの高いリードを抽出します。こうして抽出した顧客には最適なタイミングで製品やサービスを提案することで、より効率的なリード獲得や営業活動に繋がり、最終的な受注や成果向上が可能です。
リードクオリフィケーションを理解し、正しい方法で運用・活用していくことが、BtoBのリード抽出・獲得・育成・受注率向上に直結するのです。
リードナーチャリングとの違い
リードナーチャリングとリードクオリフィケーションはデマンドジェネレーションという一連のマーケティング活動における異なる役割を持ちます。
リードナーチャリングは獲得した見込み顧客を段階的に育成し、関心や興味を高めて見込み度の向上を目指す活動です。施策としては、メール配信やセミナー、Webサイトでの情報提供などを通じて信頼関係を構築します。
一方、リードクオリフィケーションはこの育成されたリードの中から、製品やサービスに対して具体的な関心や購買意欲が高まり、営業アプローチに移行できる段階にある顧客を抽出する活動です。
ナーチャリングは「育成」が主な目的なのに対し、クオリフィケーションは「抽出・選別」が主な目的と言えます。このプロセスを適切に分けて設計・管理することで、その後の営業や顧客サポートの効率化・成果向上につなげることができます。
リードクオリフィケーションが必要な理由
営業活動はマーケティング活動のようにツール等で自動化できる部分が少なく、多くの人手や時間が必要です。受注確度の低いリードが営業部門に渡った場合、成約までのコストや時間が多くかかる上、成果に結び付かないことも多くなります。これでは営業部門の業務効率が悪化し、生産性が下がる要因となります。
リードクオリフィケーションを実施することで、見込み度の高い顧客のみを選別できるようになり、営業部門は優先順位を明確にしたアプローチが可能です。これにより業務フローの無駄を省けるだけでなく、商談や受注に結びつく確度の高い案件に集中できるため、営業活動全体の成果を上げられます。
最終的には効率的なリード育成・抽出が、企業としての売上・事業成果の向上にもつながります。そのため、リードクオリフィケーションの導入はBtoB企業にとって非常に重要なポイントです。
リードクオリフィケーションの具体的な手順
次にリードクオリフィケーションを実施する際の具体的な手順を紹介します。
STEP1. リードをセグメントでわける
リードクオリフィケーションの最初の工程は、リードを条件や属性ごとにいくつかのセグメントに分けることです。ここでのセグメントとは、特定の基準をもとにターゲットを複数のグループに分類することを指します。具体的には以下のような情報を活用してグループ分けを行います。
- 企業の規模や業種
- 担当者の役職や役割
- 製品やサービスへの関心度、検討度合い
- 初回接点(セミナー参加、資料ダウンロードなど)
このような基準でリードを把握することで、アプローチすべきターゲットや最適なコミュニケーション方法を検討しやすくなります。
どのようにセグメント分けするのが最適なのかは、商材・サービスによって異なります。過去の商談履歴(リード獲得から受注までのプロセス)を参考に仮説立てて、分けるようにしましょう。
STEP2. カスタマージャーニーマップを作成する
次に、セグメントごとにカスタマージャーニーマップを作成します。カスタマージャーニーマップは、リードが顧客化・成約するまでの一連のプロセスを可視化したものです。自社のサービスや製品に関心を持つ段階から、サイトへのアクセス、資料ダウンロード、セミナー参加といった行動、最終的に購買に至るまでの道のりをまとめて定義します。
そのためには、まず想定するペルソナ※を明確に設定したうえで、それぞれの段階で見込み顧客がどのような行動や感情を持つかを整理すると効果的です。カスタマージャーニーマップはリードクオリフィケーションだけでなく、さまざまなマーケティング施策や活用方法で役立ちます。購買までの流れを把握することで、より効果的な情報提供やタイミングの良いアプローチが可能となります。
- ペルソナ:マーケティングにおけるペルソナとは、自社のサービスや商品を利用している典型的な顧客像を指します
STEP3. シナリオ設計を行う
次にカスタマージャーニーマップを参考にしつつ、どんなシナリオでリードを次の段階へと導くかを設計しましょう。このシナリオ設計では、それぞれのセグメントに所属する顧客像や抱える課題の特定、どんな情報やコンテンツを提供すれば態度変容が期待できるかを具体的に考えます。さらに、その結果どんなアクションを取ってもらうべきか、実施タイミングと手法を整理します。
シナリオは、営業チームにも共有し、全員が同じ方針で活動できるようにしておくことも不可欠です。シナリオごとに分析や改善を継続的に行うことで、その精度を高めることもポイントとなります。
STEP4. スコアリングを設計する
シナリオ設計が完了したら、リードの行動や属性に対して点数をつけて興味や関心の度合いを数値化する、スコアリングの設計を行います。たとえば「Webサイトの資料をダウンロードしたら5点」「セミナー参加で10点」など、行動内容ごとに基準を設けてスコアを設定します。これにより、リードの購入意欲や検討度合いがどこまで高まっているかを客観的に把握することが可能です。
スコアリングは設計した時のまま運用し続けるのではなく、実際に行動パターンなどのデータをもとに、定期的な見直し・改善が欠かせません。リードクオリフィケーションの精度が上がれば、営業活動の効率や成果も大きく向上しますので、データの蓄積を活用して基準や点数配分をアップデートしていきましょう。大体のMAツールにはスコアリングや分析の支援機能があるため、導入を検討するのもおすすめです。
STEP5. 設計した内容を基に運用開始
カスタマージャーニーマップを完成させ、シナリオまで設計できたら、いよいよ現場の運用に落とし込んでいきます。運用フェーズではシナリオ設計に従い、それぞれのリードに合わせたメール配信やWebサイト上でのアプローチ、資料提供、セミナー案内のタイミングなどを具体化し実施しましょう。
営業・マーケティング部門が連携して設計内容やシナリオを共有し、担当ごとにサポート体制や役割を明確にしておくことで、自社の活動を無駄なく効率よく進めることができます。
STEP6. 効果検証・改善
セグメント分け、シナリオ設計、スコアリングなど、リードクオリフィケーションの各ステップで決めた施策はあくまで仮説としてのスタートです。
運用を進める中で、顧客行動や反応から新たな課題や改善点が見えてきます。例えば、「特定の行動が予想より受注確度に影響している」「想定と違うタイミングで態度変化が起きている」など、実施しないと分からない事実が次々発見されます。
こうした新しい情報を定期的に分析し、手法や基準の見直しを実施することで精度を上げ、企業の一連のマーケティング活動全体のパフォーマンス向上に繋げるようにしましょう。
リードクオリフィケーション実施の際のポイントや注意点
リードクオリフィケーションを成功させるには、単に手順通りに行うだけでは十分ではありません。いくつか注意すべきポイントがあります。
- 明確な目標を設定する
- 通知環境を整えホットリードの機会損失を防ぐ
- 部門間の連携を大切にする
- MAツールのスコアリング機能を活用する
- 定期的にスコアリングやシナリオの設計を見直す
これらのポイントを意識して運用することで、リードクオリフィケーションの成果を最大化しやすくなります。
明確な目標を設定する
リードナーチャリングやリードクオリフィケーションを行う際には、最初に何を目指して運用・活動するかという目標(KGI)の設定が大切です。たとえば「売上10%アップ」「商談件数の大幅増加」など、具体的な指標を決めることで、マーケティング部門と営業部門双方が共通の判断基準で活動しやすくなります。
目標達成へ向けた中間指標(KPI)も明確にすると、今何を優先して取り組めば良いかがわかります。こうした目標や基準の認識を全社・部門間で共有することは、営業活動の効率やリード獲得の成果最大化に直結します。
通知環境を整えホットリードの機会損失を防ぐ
リードの行動データの中には、タイミングがとても重要なものがあります。特に「製品ページへのWebアクセス」などは、すぐにでも購買や導入を検討している可能性が高いサインです。競合他社の製品もリードが比較検討していることが多いため、このようなホットリードにはできるだけ早く、適切なアプローチを行う必要があります。
MAツールの通知機能を利用すれば、リードが動いたタイミングを逃さず把握でき、素早いフォローアップの実現が可能です。これにより、ホットリードの獲得チャンスを最大限に活かせるようになります。
部門間の連携を大切にする
BtoBマーケティングの現場では、マーケティング部門と営業部門の連携こそが成功のカギです。典型的には、マーケティング部門がリードを育成・抽出し、営業部門へと情報を引き継ぎます。その際できるだけ顧客の属性や行動履歴などの具体的な情報もあわせて共有することで、営業部門が精度の高いアプローチを行いやすいです。
また営業部門が既存顧客との関係情報や新たな発見をマーケティング部門にフィードバックしていれば、全体のプロセス設計やスコアリングの精度も向上します。情報連携・共有体制を強化することで、両部門の活動が効率的かつ効果的に進むようになります。
MAツールのスコアリング機能を活用する
MA(マーケティングオートメーション)ツールには用途ごとに多様なスコアリング機能が搭載されています。特に人員リソースが限られている企業にとっては、この種の自動化ツールの導入は業務効率の劇的なアップに直結します。
たとえば、Webアクセス分析、メールの開封やクリック判定、資料ダウンロードやセミナー参加の履歴まで連携し、ひとつひとつの行動を自動でスコア化・管理することが可能です。この結果としてホットリードの抽出から連絡、商談への移行プロセス全体の省力化を実現できます。
スコアリング機能を活用すると人手によるミスや見落としも減らせるため、リードクオリフィケーション作業の精度向上、成果最大化を目指したい場合におすすめです。最新のMAツールは担当者や部門間の情報共有もサポートできるので、マーケティング基盤の強化を図りたい企業にも適しています。
定期的にスコアリングやシナリオの設計を見直す
カスタマージャーニーマップやスコアリングシナリオは、定期的な見直しが重要です。「どのような行動時に何点スコアを付与するか」というルールは、マーケティング活動で得られた新しいデータや仮説変更に応じて更新していく必要があります。
初めは過去事例や仮説をもとに設計しても、継続的に分析・検証を進めることで、リードの検討度合い判断や優先付けの精度を高めていけます。社内の共有データや顧客動向レポートもあわせて管理・検討しましょう。シナリオやスコアリングのアップデートを怠らず、日々変わるリード行動にあわせて施策の改善を続けることが、商談化率や獲得効率のアップへ直結します。
まとめ:リードクオリフィケーションで大切なポイント
リードクオリフィケーションにおいて、ホットリードを正確に見極めることは営業成果や売上向上に直結します。ホットリードを精度高く抽出できれば、見込み度の高い顧客をもれなく商談・受注につなげることができ、事業の成長スピードも上がります。一方、まだ検討段階のリードを無理に営業へ回すと成約率の低下やリソースの無駄遣いにつながるため、取捨選択は慎重に行いましょう。
また、購買意欲の高いホットリードは多くの場合競合他社の製品とも同時に比較検討しています。自社が素早くサインをキャッチし、最適なタイミングでアプローチできるかがリード獲得の勝敗に大きく響きます。
成果を最大化するために、精度と即時性を両立したリードクオリフィケーションの運用を心がけましょう。本記事のポイントを参考に、ぜひ自社の課題や運用方法を見直し、さらなる成果アップへとつなげてください。