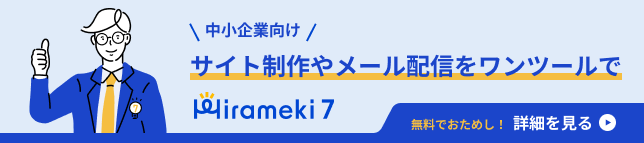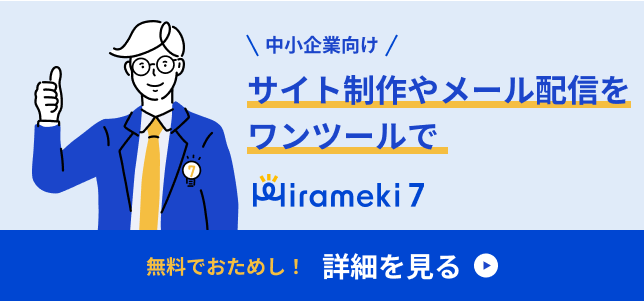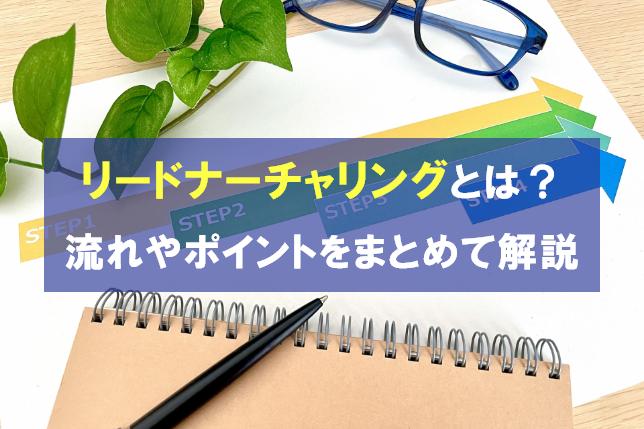ホワイト ペーパーとは、リード獲得や顧客の課題解決に役立つため、多くの企業が活用しています。
本記事では、その意味や種類、作成に欠かせないポイントを具体的に解説します。今後リード獲得施策を強化したい方はぜひご確認ください。
目次
ホワイトペーパーとは?
ホワイトペーパー(White Paper)とは、企業が見込み顧客を集めるために提供する資料で、顧客の課題解決策や興味に基づいた情報などをまとめた報告書です。
マーケティングの手段としてBtoBの場面で多く使われ、語源は調査レポートの白書だといわれています。商材との相性次第でリード獲得の成果が期待でき、営業活動でも活用しやすい特徴があります。
たとえば、導入事例や課題解決の具体策を提示すると、顧客が自社サービスや商品に興味を持ちやすくなるメリットがあります。企業側もWebサイトからダウンロード可能にしておけば、リード情報を収集しながら効果的な広告や分析へつなげることが可能です。
サービス紹介資料とホワイトペーパーの違い
「サービス紹介資料」は、製品の機能や価格を直接説明しながら購買を促進する情報が中心ですが、「ホワイトペーパー」は、顧客の課題を掘り下げて問題解決へのサポートを示す点で大きく異なります。
後者は潜在層や検討段階のユーザーにも有益となり、提供企業の専門性をアピールできるため、より幅広いリード育成が可能です。自社のサービスを説明する前段で顧客の理解を深める施策として、ホワイトペーパーの存在は欠かせません。
ホワイトペーパーの種類
一口にホワイトペーパーといっても、以下のようなさまざまなテーマがあります。順に概要を解説します。
- ノウハウ紹介
- 調査レポート
- テンプレートやチェックリスト
- セミナーや展示会等のイベントレポート
- カオスマップやポジショニングマップ
- 事例紹介集
ノウハウ紹介
自社が蓄積している専門ノウハウを、読み手に向けて分かりやすくまとめたホワイトペーパーです。課題解決に直結する具体的な知識を提供すると、顧客が興味を示しやすいです。
しっかりとユーザーのニーズに応えたうえで、自然な形でサービス・商材の紹介に繋げることができるとより良い施策となります。
調査レポート
独自で調査したアンケートなどのデータをまとめたホワイトペーパーです。市場に出回っていない知見や、トレンドにあった内容を提供すると、顧客は新鮮な情報として興味を抱きやすいです。
たとえば、業界動向やユーザーのニーズを分析したレポートをまとめれば、検討段階のターゲットだけでなく、情報収集重視の層も惹きつけられます。信頼感を得られた企業はリード化が進みやすく、営業活動にも良い影響を与えます。
テンプレートやチェックリスト
実務ですぐ使えるテンプレート、あるいは状況確認に便利なチェックリストを中心にまとめたホワイトペーパーです。最近では、AIチャットで利用できるプロンプトを配布するケースも増えています。
自ら問題を解決したいと考える人の関心を獲得しやすい点が特徴です。ただし、商談化には繋がりにくい層にはなるので、リード情報を獲得した後に、どのように継続してアプローチしていくかも重要です。
セミナーや展示会等のイベントレポート
開催したセミナーや展示会などのイベント内容をレポートにして、まとめたホワイトペーパーです。ウェビナーの参加特典として、終了後にホワイトペーパーとして内容をまとめたものを配布するケースが多いです。
資料をダウンロードした人が、次回のセミナー参加や製品の導入を前向きに検討してくれる可能性があります。遠方のため現地に行けないユーザーへもサービスを訴求でき、オフラインでの取りこぼしを防げる点が魅力です。
カオスマップやポジショニングマップ
同じ業界に存在する多くのサービスや製品を一目で把握できるように、カオスマップやポジショニングマップを作成するタイプです。競合比較を視覚的にまとめることで、ユーザーが興味を引きやすくなるメリットがあります。潜在層のリード獲得と相性の良いホワイトペーパーです。
事例紹介集
既存顧客の情報をもとに、「導入に至った経緯」や「導入したことによる成果」をまとめたホワイトペーパーです。顧客のご協力が必要になるため、掲載許可や差し替えなど工数が発生する部分もありますが、一度テンプレートを作成してしまえば、ホワイトペーパーの作成自体は簡単に行うことができます。
実際の経験談が示されているとユーザーは購買後のイメージを作りやすくなるため、自社の商材・サービスを検討している層に対して、確度を高めることができます。
ホワイトペーパーを作成する際のポイント
ホワイトペーパーを作成する際は、読者が求める内容に焦点を合わせるのが重要です。以下3点をポイントに作成するようにしましょう。
ターゲット層のリテラシーにあわせて作成する
読者が欲しがる情報量や専門用語のレベルはターゲット層によって異なるので、あわせることが大切です。
初心者向けの内容なら専門知識が浅いユーザー向けに分かりやすい説明・表現を心がけると、ストレスなく理解してもらえます。より調査が深いレポートを作る場合は、背景データや考察を充実させ、説得力ある内容を取り入れると満足度が高まります。
事前に想定ターゲットを分析し、読者のリテラシーにあった内容・表現になるようにしましょう。
ユーザー視点で作成することを心がける
ホワイトペーパーで、商品やサービスを前面に押し出すだけでは、読者が自分の課題を解決する手段として認識しづらいです。ユーザーの視点に立って、「課題の解決策や役立つ情報」を一番に伝えていくことが大切です。
ユーザーが抱える困りごとを踏まえ、ニーズに合う情報を的確に提示すると、結果的に自社への信頼が上がります。市場でよくある悩みや、新しいマーケティング施策に関する疑問点などを事例とともに解説することで、顧客視点の資料として価値が増します。そのうえで、自然に自社の製品やサービスを紹介する形にすれば、読者は営業色を感じにくく、ポジティブな印象を抱きやすいです。
読み終えたときに「これは役立つ」と思ってもらうことを最優先に内容を検討するようにしましょう。
商材・サービスの押し売りは避ける
前述したように、ホワイトペーパーは営業資料と異なり、顧客の課題解決を後押しする性質が重視されます。
必要以上に製品特長を並べると、読者がセールス色を警戒してしまうかもしれません。顧客の立場を考えた構成にし、まずは課題と解決方法を提示するアプローチを心がけ、興味を持った人が自然に次の情報をチェックできるフローになるようにしましょう。
ホワイトペーパーの活用例
ホワイトペーパーを作成した後は、以下のような施策を実施し、リード獲得に繋げていきましょう。
自社サイトに掲載する
最も手軽な方法は、自社サイトにホワイトペーパーを掲載して訪問者からのダウンロードを促すことです。費用がかからない利点がありますが、思うように数字が伸びない場合はSNSでの告知や広告訴求等の流入数を増やす施策が必要です。
また、新しいホワイトペーパーを作成したときは、サイトのトップページやブログ記事などにリンクを設置すると目に触れる機会が増え、ダウンロード数向上に繋がりやすくなります。
メルマガで配布する
次に、メルマガ配信で、文章内にホワイトペーパーのダウンロード導線を用意して、顧客や見込み顧客に配信する方法です。
たとえば、製品導入に役立つ課題解決のレポートを送れば、段階的に利用意識が向上します。すでに契約中のユーザーには導入事例をまとめた資料を届けると、追加でサービスを使ってもらえる可能性があります。
複数のホワイトペーパーを用意しておき、それぞれの顧客層にあわせて紹介すれば効果的でおすすめです。メルマガ施策であれば、継続的に接点をもつことができるため、リード育成施策としても活用しやすい手段になります。
ウェビナーなどの参加特典として配布する
ウェビナーや展示会などのイベント参加者に、ホワイトペーパーを特典として配布するのも一つの手段です。ニーズが高まっている状態で配布することができるため、資料をじっくり読み込んでもらいやすいです。
オンライン配布だけでは接触できない層へもアプローチでき、サービスや商品の導入検討を促すきっかけが増えます。
他社メディアに掲載する
多くの見込み顧客が集まる媒体でホワイトペーパーを紹介してもらうと、リードを獲得しやすくなります。掲載費用や条件の調整は必要ですが、広いユーザー層へコンテンツを届けられる利点は大きいです。
ただし、自社サイトを通じてダウンロードしたユーザーに比べると、自社への認知・理解度は低い可能性が高いため、ダウンロード後の顧客を育成する施策をあらかじめ講じておく必要があります。
ホワイトペーパーのダウンロード数を増やすコツ
手間をかけて作ったホワイトペーパーでも、ダウンロード数が伸び悩むケースがあります。その場合は、以下をポイントに改善を図るのがおすすめです。
ダウンロードフォームの入力項目は最小限にする
ホワイトペーパーのダウンロードフォームは、入力項目を最低限にするようにしましょう。入力欄が多すぎるとユーザーが面倒に感じ、途中でやめてしまう恐れがあります。
営業活動で詳しい情報が欲しくなる気持ちはありますが、項目によっては、案件化した際や商談が進んだタイミングでも間に合います。まずは、ハードルを低くする施策を優先し、ダウンロードまでの動線を短く設定することで成果を最大限伸ばすようにしましょう。
興味を引くタイトルやサムネイルを作成する
ホワイトペーパーをダウンロードしてもらうには、最初の視覚要素とタイトルが大きな役割を持ちます。一目で内容が伝わる表紙デザインや、ユーザーの関心をくすぐるコピーを付けるとダウンロード率が上がりやすいです。
- 「初心者向け」「○○にお悩みの方」等、ターゲットを明記
- 「○% 改善」「ダウンロード数○件」等、具体的な数値を訴求
- ベネフィットを入れる
などを意識し、タイトルやサムネイルを作成しましょう。また、ABテストを実施することでより成果がとりやすくなるためおすすめです。
自社サイト以外にも掲載範囲を広げる
コンテンツをより多くのユーザーに届けるには、自社サイトだけではなく多様な媒体でダウンロードを促す戦略が有効です。手間や費用がかかる場合もありますが、外部メディアを活用すれば新しいリードを獲得できます。
たとえば、広告スペースを購入したり、業界専門サイトで掲載してもらったりといった方法です。自社だけでは接点を持ちにくい顧客にリーチでき、追加のマーケティング活動へもつなげやすいです。
ターゲットごとに訴求内容を変える
読み手が求めているテーマや課題、検討段階に沿ってホワイトペーパーの切り口を変えると、ダウンロード数や満足度が高まります。複数のバリエーションを作成することであらゆる段階のユーザーをカバーでき、自社への関心を高めるチャンスになります。
どのターゲット層に対してどういったホワイトペーパーを届けるのかを明確にし、ターゲット層にあわせてコピーやタイトルを検討するようにしましょう。
ホワイトペーパーのダウンロードフォームを用意するならHirameki 7
Hirameki 7の「フォーム」機能では、月額800円(税別)で最大5つまでのダウンロードフォームを作成することが可能です。
(※利用量にあわせて追加することも可能です)
また入力された情報は「名刺管理」機能に連携し、「メール配信」機能で一斉メールを送ることもできるため、リード獲得後のアプローチまで1ツールで行うことができます。今後、ホワイトペーパーを用いたマーケティング施策を強化されたい方は、以下からHirameki 7での活用シーンをご確認ください。