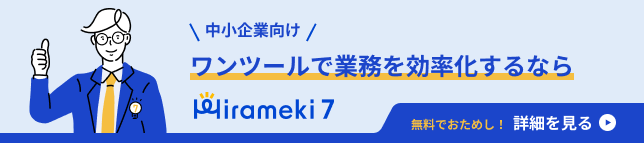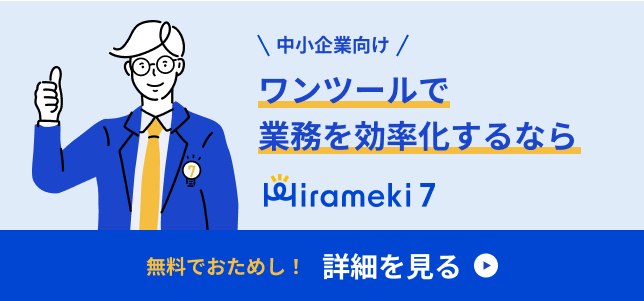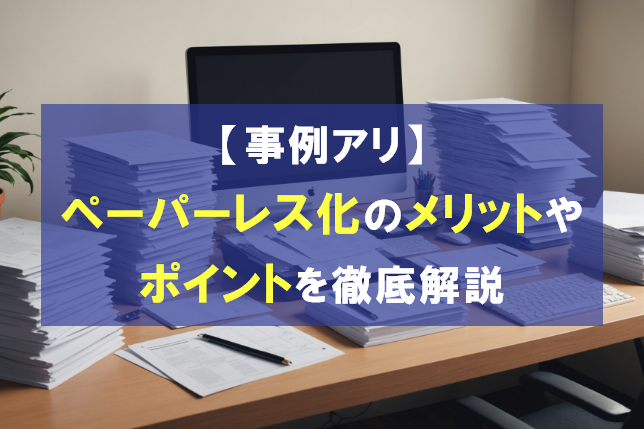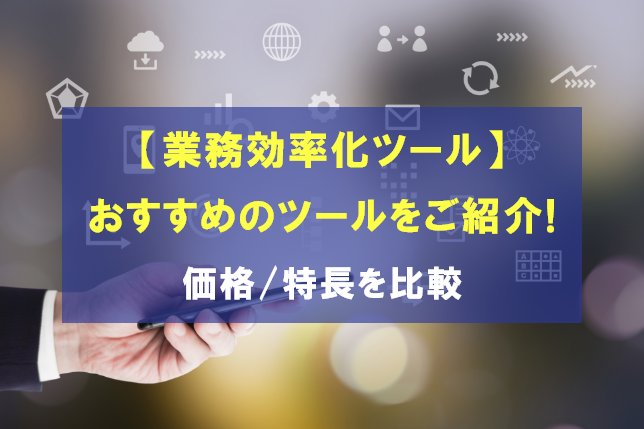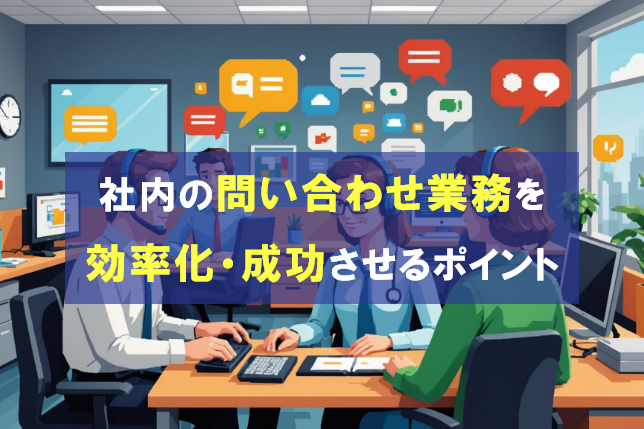
社員からの問い合わせ業務は、企業が成長するほど件数や内容が増え、担当部門や部署の負担も大きくなります。対応に追われて本来の業務に集中できず、時間やコストが膨らむ課題を抱えている会社は少なくありません。
こうした状況を改善するためには、効率的な問い合わせ管理やFAQ整備、マニュアル作成、チャットボットやAIツールの活用など具体的な対応方法が必要です。
この記事では、よくある課題や効率化を実現するための対応例、成功のためのポイントまで詳しく解説します。問い合わせ対応の負担を軽減し、業務効率や社内の生産性向上を目指す方におすすめの内容です。
目次
社内の問い合わせ業務における課題
社内の問い合わせ業務には主に以下2つの大きな課題があります。
社内の問い合わせに対応しきれていない
問い合わせ件数が増えたり、部署や担当者が限られたりすると、すべての社内問い合わせに短時間で対応することが難しくなり、「対応が遅れる」、「一部が対応漏れが発生する」などの問題が発生するリスクが高まる点が1つめの課題です。
問い合わせ業務の効率化に繋がるシステムを導入していない場合や、対応工数を削減するためのマニュアルやFAQを用意できていない場合に、特に発生しやすい課題です。
問い合わせ対応が属人化している
「問い合わせ対応が属人化」してしまうのも課題のひとつです。
社内問い合わせの内容によっては、特定の担当者にしか分からない業務や専門知識が必要となりがちです。この状況が続くと、担当者が不在の際には「対応品質の低下」や「そもそも誰も答えられない」といった属人化の問題が発生します。
例えば、特定のツールの設定や運用方法を一人だけが理解している場合、その担当者が休暇中だと問い合わせが停滞します。これは「ひとり情シス」と呼ばれるような小規模体制のヘルプデスクで特に起こりやすい課題です。
社内の問い合わせが増える原因
社内の問い合わせが増加する背景には、いくつかの典型的な課題があります。まずマニュアルやルールの運用に問題がある場合、適切に情報が活用されず、同じ問い合わせが繰り返し発生しやすくなります。マニュアルやFAQの内容が古いままだと、社員は最新の運用方針や対応方法を把握できず、自己解決できないケースが多くなるでしょう。
さらに、自己解決の意識が社内全体に浸透していないと、ちょっとしたことでもバックオフィスや担当部署へすぐに質問が集まってしまいます。
まとめると
- マニュアル類の管理や更新が追いついていない
- 最新情報が社内で共有されていない
- 社員一人ひとりが自分で情報を探す習慣がない
が主な社内の問い合わせが増える原因です。これらを解決することで、問い合わせ件数の抑制と担当者の工数削減が期待できます。
社内の問い合わせ数や対応時間を削減する方法
社内の問い合わせ数や対応時間の削減には、問い合わせ部署への集中を防ぐ仕組みづくりが効果的です。まずは社員が自身で問題を解決できる環境を整え、問い合わせ件数自体を減らす方針に取り組むのがおすすめです。
FAQやマニュアルの整備、自己解決を促すツールの導入などを活用し、社員の自己解決率が上がれば、部署ごとの問い合わせ対応負担も軽減されます。結果として全社業務の生産効率向上やコスト削減に直結します。
社内に解決方法を周知する
社内でバックオフィスへの問い合わせ数を削減したい場合、まずその必要性を全社員にしっかり伝えることが大切です。具体的にどのような問題やコストが発生しているかを明確に説明し、全員で課題を共有することがポイントです。
問い合わせ対応は企業全体のコストにもつながるため、まずは自己解決に前向きに取り組む意識改革が求められます。同時に、FAQやチャットボット、マニュアルといった自己解決のためのシステムがすでに整備・設置されていることもきちんと周知しましょう。その際はツールの設置場所や利用方法も分かりやすく説明し、使い方に迷わないよう広報体制を整えることが重要です。
マニュアルを作成する
社内問い合わせに対する回答を明確にまとめたマニュアルを作成しておくことで、業務対応を大幅に効率化できます。回答内容を一元管理し、社内で広く共有すれば、担当者が不在でもスムーズな対応が可能です。また、よくある質問や簡単な解決方法などをマニュアルやFAQで公開することで、社員自身が調べて自己解決する動きが生まれ、問い合わせ件数そのものの削減にも貢献します。
ただし、マニュアル作成はポイントを押さえて行わないと逆に工数が肥大化するため、効率的な整備方法や運用ルールを事前に検討し導入することが重要です。運用時にも定期的な見直しや改善を行い、常に最新情報が反映された状態を保つようにしましょう。
問い合わせ対応用にテンプレートを用意する
同じ内容の問い合わせが何度も寄せられる場合には、対応テンプレートを作って標準化するのが効率化の鍵です。毎回個別に考えて回答していると、担当者の負担が大きくなります。
テンプレート化によって手間や考える時間を大幅に削減できるだけでなく、どの担当者が対応しても基本的に同じ内容の回答になるため、社員全体で均一な知識共有が実現します。テンプレートは問い合わせ管理システムやチャットボットと連携して運用することで、より迅速かつ正確な対応体制が整えることが可能です。
問い合わせ対応を一元で管理・共有する
問い合わせ対応を一元で管理・共有できる環境を整えることも大切です。
社内問い合わせがメールや電話、LINEなど複数手段で発生すると、管理が煩雑になりやすいです。窓口やツールがばらばらだと問い合わせの進捗や履歴を把握しにくく、回答漏れのリスクも高まります。Googleスプレッドシートや、問い合わせ管理システムなどの導入により、すべての対応状況や履歴を一元的に管理できる環境を整えましょう。
また、こうした一元管理環境では情報の集約やデータベース化がしやすく、傾向分析やさらなる件数削減施策の立案に役立てることもできます。
チャットボットやWikiツールなどのシステムを導入する
定型的な社内問い合わせが多い場合、チャットボットをはじめとしたシステム導入が非常に有効です。あらかじめFAQやマニュアルからよくある質問を収集・整理し、チャットボットに登録することで、社員がいつでも即座に自分で回答を得られる環境が整います。
人事や経理のように反復的な質問が多い部署では、特に自動応答の効果が大きく、担当者が個別対応にかける工数を削減しつつ迅速な社内サポートが可能となります。回答内容の定期的な更新や、問い合わせログの分析も忘れずに行うことで精度と利便性を高く維持できます。
問い合わせ削減施策を行う際のポイント
次に実際に問い合わせ削減・効率化施策を実施する際のポイントをご紹介します。システムを導入する際や、問い合わせ対応の改善を図る際は以下をポイントに実行するようにしましょう。
何が課題かを明確にしたうえで解決策を選ぶ
社内問い合わせ業務を効率化するには、まず現状どこに課題があるのかを明らかにすることが肝心です。課題の内容次第で適切な解決方法や導入するシステムが変わるので、現場へのヒアリングやアンケートなどを実施し、従業員の悩みや疑問、業務のどこに時間や手間が発生しているかをしっかり洗い出すことが重要です。
この分析の結果をもとに、FAQの充実、チャットボットの導入、問い合わせ管理ツールの利用など、優先度や必要性を持って具体的な施策を検討しましょう。このように課題解決のプロセスを明確にすることで、一時しのぎではなく本質的な業務改善につながります。
常に最新の情報を得られる環境を整える
FAQやナレッジベースの情報は放置しているとすぐに古くなり、利用されなくなるリスクがあります。問い合わせ件数の削減や業務効率化の観点では、常に情報を最新に保つ整備や定期的な更新が不可欠です。
既存の環境で解決できなかった問い合わせに対して、都度システムを更新したり、定期的な見直しを行う機会を用意したりするなど、常に最新の情報を得られる環境づくりが大切です。
システムを導入する場合は社員の使いやすさを重視する
FAQやチャットボットなどのツールは、社内問い合わせ数削減の強力な手段ですが、導入時には社員のITスキルや使いやすさを重視することが極めて重要です。機能面が優れていても、社員がうまく使いこなせなければ運用が定着せず、期待した効果が発揮できません。
ツールを選ぶ際は、ユーザーインターフェースが分かりやすいか、操作がシンプルかなど、社員目線に立った設計ポイントを確認することが大事です。利用現場の負担を増やさない環境設定や研修もセットで導入することで、十分な活用効果を得やすくなります。パフォーマンス向上には使いやすさの優先が不可欠です。
継続的に状況確認・ブラッシュアップを行う
システム導入後も従来の問題が解消されないことや新たな課題が発生するケースもあるため、定期的な状況確認とシステムの見直しは欠かせません。FAQや回答内容の鮮度が下がったり、社内状況の変化に対応しきれなかった場合、それまで築いた効率化が無駄になるおそれがあります。
定期的なアップデート作業や運用プロセスのブラッシュアップを習慣化し、継続的な業務改善につなげることが管理部門の重要な役割となります。
社内の問い合わせ業務の効率化に繋がるツール
社内の問い合わせ業務効率化に役立つツールとして、さまざまなシステムが提供されています。本記事では大まかな種類と例となるツールをご紹介します。
コミュニケーションツール
1つ目の手段は、TeamsやSlackなどの「コミュニケーションツール」です。社内問い合わせ専用のチャンネルを用意し、質問者以外も参照できる環境で対応することができます。すでに別の用途でコミュニケーションツールを利用している場合は、導入コストをかけずに活用することができるのでおすすめです。
また、TeamsであればOneNote、Slackであればcanvasを「社内Wiki」として活用することで、問い合わせ削減に繋げることができます。
ただし、あくまでコミュニケーションツールになるため、検索のしやすさは専用ツールに比べると劣る部分があり、過去の問い合わせを参照しづらいため注意が必要です。
AIチャットボット
次の手段として「AIチャットボット」が挙げられます。社内情報をAIに学習させチャット形式で問い合わせに対して自動で対応させることができます。具体的なシステムとしては、社内問い合わせさくらさんやHiTTOなどが該当します。チャット形式になるので、人に質問する時と同じ感覚で利用できる点がメリットです。
また、システムによってはスマートフォンに対応していたり、SlackやTeamsなどのコミュニケーションツールに連携して使えたりするなど、利用促進がしやすい設計になっているのも安心です。
ナレッジ・FAQ管理システム
最後に、社内問い合わせに特化した「ナレッジ・FAQ管理システム」を活用する方法です。具体的なシステムとしては、ナレッジリングやNotePMなどが挙げられます。社員向けにマニュアルやFAQを作成し、充実した検索機能で、社員自身で解決できる環境を整え、問い合わせ数自体を削減することが可能です。
また、検索で解決しなかった時の利用できるコミュニティ機能や、エクセルやPDFなどの添付ファイルの中身まで検索対象とする機能など、社内問い合わせ時に起こる問題を解決する機能が揃っています。機能が充実している分、他手段に比べコストが高くなる傾向にあるため、目的・課題に沿って導入すべきか判断するようにしましょう。
まとめ|課題を明確にし、社内問い合わせ効率化を実現
社内問い合わせは、バックオフィス業務に大きな負担をかけることが多く、対応件数や内容によって通常業務が妨げられるケースも見受けられます。本記事で解説したとおり、問い合わせ削減のためには「自己解決できる環境・意識を整えること」と「対応業務の効率化に繋がるシステム導入」の2つの軸を意識した取り組みがポイントです。
FAQ、チャットボット、マニュアルの整備により自己解決を促し、問い合わせ管理ツールを活用することで業務の属人化や抜け漏れを防ぐようにしましょう。