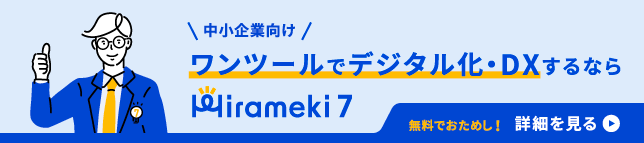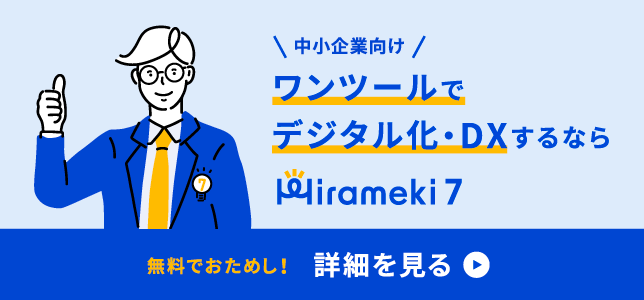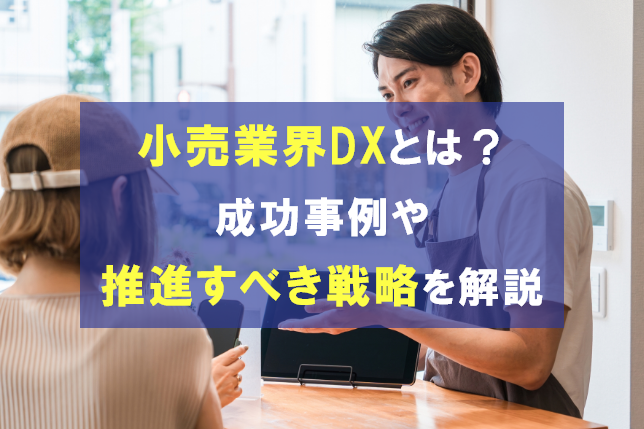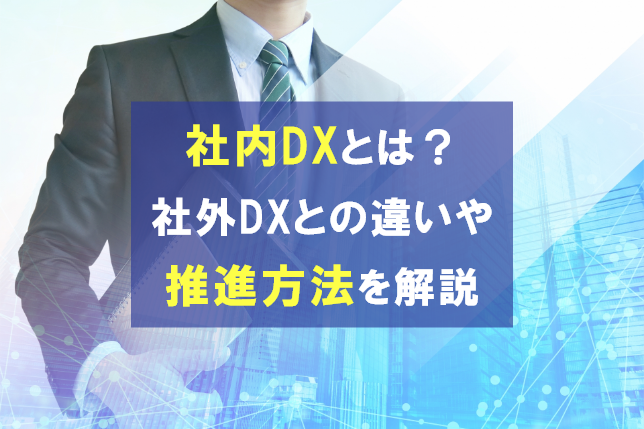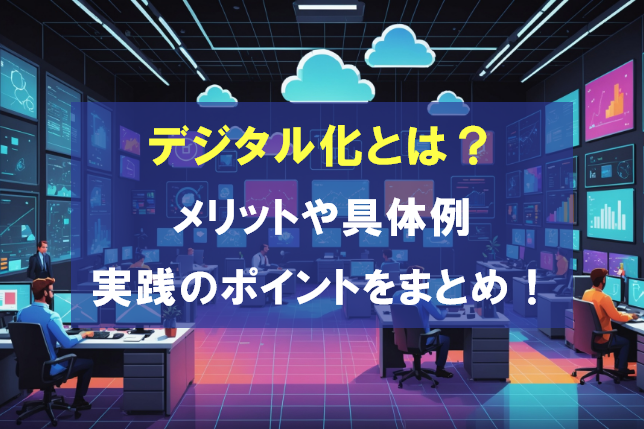
近年、社会やビジネスの急速な変化により、多くの企業が業務効率化やコスト削減といった課題に直面しています。特にAI技術の革新が進む現在、デジタル化の推進は競争力を維持・強化するために欠かせない取り組みとなりました。
本記事では、デジタル技術を活用した業務改革の意味やメリットをわかりやすく解説します。また、ペーパーレス化や業務自動化などの具体例、実際に自社で進める際のポイントも紹介します。働き方改革や業務効率化を実現したい方に有効な情報になるので、ご興味のある方はぜひ参考にしていただければ幸いです。
目次
デジタル化とは?
デジタル化は、アナログ手法に頼っていた業務プロセスをデジタル技術を使って自動化・効率化する取り組みです。内容としては、紙ベースで保管していた書類のデータ保存や、対面会議の代わりにビデオ会議システムを活用するなど、幅広い業務改善を含みます。
一般的に、デジタル化はその進展の段階に応じて、次の3つに分類されます。※
- デジタイゼーション(アナログデータのデジタル変換)
- デジタライゼーション(ビジネスモデル自体の変革や新たな価値の創出)
- デジタルトランスフォーメーション(DX:仮想と現実を融合し業界の構造まで革新する)
それぞれ企業全体の成長や課題解決に貢献しますが、一般的にデジタイゼーション→デジタライゼーション→デジタルトランスフォーメーションの順で段階的に進みます。
企業がデジタル化を進めるには、自社の現状やリソース、業務効率や管理の課題を丁寧に分析し、段階ごとの適切な施策やサービスを検討し導入していくことが重要です。ペーパーレスやオンラインワーク、データ管理等の目的や違いも明確にし、必要なデータやシステムを選定して効果的に活用することで、ビジネスプロセス全体の効率化や競争力の向上につなげることができます。
このように、業界や会社ごとに状況の把握や課題解決ポイントはさまざまですが、デジタル化には紙業務やアナログ情報の電子化にとどまらず、ワークフローの自動化や企業変革を支えるデジタルトランスフォーメーションへの発展が求められます。今後は自社の取り組み状況を確認しつつデジタルトランスフォーメーション推進を含めた多角的な取り組みを検討、実現することが求められるでしょう。
- 経済産業省「DXに関する経済産業省の施策紹介」
デジタイゼーション
デジタイゼーションとは、従来の業務プロセスは今まで通りにしつつ、アナログで扱われていた情報や資料をデジタルデータへ変換・保存する仕組みです。一般的に「デジタル化」と呼ばれるのは、このデジタイゼーションにあたります。
具体的な例は
- 紙媒体の資料をスキャンして電子データとして社内で管理
- 請求データをオンライン上でやりとり
- 電子契約や電子署名ツールの導入
- 設計図も従来の紙からCADデータ化
- 会議やミーティングを紙資料からオンライン化
- 勤怠、契約書、経費申請のペーパーレス化
などです。
こうした作業のデジタル化によって業務効率が向上し、ヒューマンエラーが減るのはもちろんデータ共有やバックアップ管理もしやすくなります。ただし、デジタイゼーションは業務プロセス自体には大きな変化を与えないため、改善領域は主に社内の効率化や管理に限定されます。企業におけるデータ活用やペーパーレス推進の第一歩として有効ですが、本格的な変革には次のステップへの展開が重要です。
デジタライゼーション
デジタライゼーションはツール導入や自動化によって、特定業務自体のプロセスを大きくデジタル化し、業務効率を一段と高めることが狙いです。経理システムに専用のITツールを入れて会計業務の効率化を図ったり、ユーザー情報に応じて求人案内を自動化したり、会議室確保や移動の手間を省くためのオンライン会議システムの導入などが該当例です。また、販売データと受発注システムを連動させて、在庫管理や材工手配を自動化することで全体のワークフロー効率も大きく変化します。
デジタライゼーションによってプロセス全体の自動化が進むと、コスト削減や従業員の業務負荷軽減、サービス品質の向上が図れるはずです。さらに新たなデータ活用や新サービスにつながる基盤を構築できることも特徴です。既存業務の枠を越えて、企業価値向上や競争力強化の手段となります。
デジタルトランスフォーメーション(DX)
デジタルトランスフォーメーション(以下DX)は、企業や組織がビッグデータやAI(人工知能)、IoT(モノのインターネット)などの先端的なデジタル技術を大規模に活用し、業務プロセスの刷新だけでなくビジネスモデルや収益構造自体を根本から変革する取り組みです。くわえて、組織文化や企業風土までもが大きく変えられるため、競争力のある新たなビジネス環境が生まれやすくなります。
具体的な事例としては、製造業で現場データをクラウドやAIで見える化し生産性向上を図る、物流企業がAIによる配車や集配ルート自動設定ツールで最適配置を実現する、不動産会社が顧客の自宅からオンライン物件案内・シミュレーションを提供するなどがあります。こうした高度なデジタル化によって、従来の常識を超えた新サービスの創出や組織改革、拠点運営の最適化、投資対効果向上が可能です。
デジタル化とDXの違い
「DX」は、企業が既存事業のみならずビジネスモデルや産業構造そのものを根本から変革し、新たな市場や価値を創り出すことです。一方で、一般的にデジタル化と呼ばれている「デジタイゼーション」は、主に現行事業の特定業務をデジタルで代替したり、品質や効率向上を目指す施策が中心になります。つまり、デジタイゼーション・デジタライゼーション・DXはすべて広い意味の「デジタル化」に含まれますが、その進展度合いによって区別されると整理できます。
一般的には、最初にデジタイゼーションやデジタライゼーションから始め、段階的にDXへと発展します。まずはデジタル化を実践し、徐々に全体のワークフローやビジネス変革につなげるプロセスが現実的でしょう。
社内のリソース・運用できる人材・予算などを考慮した際に、無理にDXに進めることは大企業にとっても厳しいことです。まず、一つ一つ社内業務をデジタル化していくことで、事業を効率化していくことを目指してみてください。
デジタル化のメリット
企業がデジタル化に取り組むことで得られる最大のメリットは生産性の向上です。生産性とは、人や資源を投入して得た成果の大きさを測る指標です。生産性向上により、同じリソースでより多く・高品質な成果やサービスが生まれ、業務プロセスもより効率的になります。
業務効率やコスト削減だけでなく、デジタル化は従業員の多様な働き方への対応や新しい業務モデルの創出など、ワークライフバランスやイノベーション創出にもつながる効果が期待できます。効率化・削減だけではなく、組織の価値やサービス品質の向上も実現できるのです。
作業効率・品質の向上
手作業や繰り返し作業をデジタル化し自動化すると、処理時間を大幅に軽減できます。同時に人的ミスを減らせるため、作業品質の安定化や効率向上につながります。作業プロセス簡素化が対応コストおよび作業時間の削減につながるのです。
結果として、労働者はこれまで以上に重要な業務や新規プロジェクトへ時間を回せるようになり、企業の付加価値向上やイノベーション創出にも結びつきます。
効率的なデータの管理・共有
クラウドストレージや案件管理ツール、社内用のwikiなどを活用すれば、従業員がどこからでも必要な資料やデータに簡単アクセスできるでしょう。
こうしたシステムを活用することでリアルタイムで情報共有ができ、伝達ミスのリスクが軽減されるため、データのバックアップ・保全対策にも有効です。結果として業務の整理や管理体制の最適化、効率的な全体運用に役立ちます。
従業員満足度の向上
業務のデジタル化は、作業効率向上による従業員の残業時間や業務負担の削減、より柔軟なワークスタイルの実現に繋がるため、従業員満足度の向上が期待できます。
デジタル化でリモートワークやテレワークを実現すると働く場所や時間の選択肢が広がり、業務ストレスが軽減され、従業員のワークライフバランスの改善を期待できるのです。結果、従業員の満足度が高まり、組織に対するエンゲージメントや好感度も向上します。
人件費・経費の削減
デジタル化を行うと自動化施策によって人的な介入が減り、紙の削減によるペーパーレスも進みます。アナログで実施していた印刷や郵送等のコストが削減できるため、人件費や経費全体の圧縮にもつながるのです。
くわえて、リモートワークなどの導入によって、オフィスの縮小や従業員の移動コストの削減といった副次的メリットも生まれます。
新サービスの創出
デジタル化が進むと、自社のデータやノウハウを活用した多様な分析が可能になります。これによって既存ビジネスモデルの無駄や改善点が明確となり、業務効率化から着手した改善活動もやがて新サービスやソリューションの開発に発展するはずです。
実際に、小売業の企業が自社商品の在庫を自動管理し、サブスクリプション型サービスに転換して新たな収益モデルを実現した事例も見られます。また、熟練者の技術をAIやセンサーで数値化・データ化し、新人教育や外部へのノウハウ提供など、働き方とサービス創出の両面で多様なメリットが得られる点も特徴です。
デジタル化の具体例
前述の通り、デジタル化をうまく取り入れることでビジネスの成果は大きく高まります。ここでは実際にどのようにビジネスの現場でデジタル化が活かされているのか、具体例をいくつか紹介します。
本記事ではデジタル化の具体例を大枠で説明しますが、更に細かい説明は以下記事で紹介しているのであわせてご確認ください。
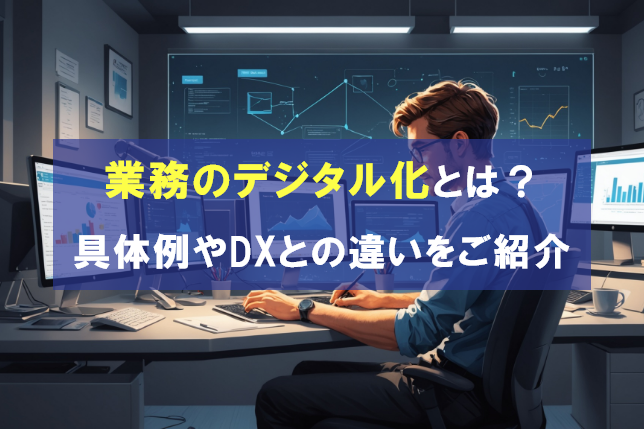
ペーパレス化
ペーパレス化は、紙で行われていた名刺交換や契約書、会議資料などをデジタルデータとして一元管理することです。
- 名刺
- 勤怠管理表
- 会議資料
- カレンダー
- 請求書、領収書
- 契約書
- 帳票
- 経費申請書
- 給与明細
- マニュアル
など、各種書類をデータ化すると、情報の共有やバックアップが容易になり、管理の手間や時間も削減できます。また、電子契約に切り替えれば、契約書への電子署名だけで済むため、郵送や紙面の保管も必要ありません。結果として、全体の業務プロセスがシンプルになります。
ペーパーレス化については、以下記事で詳細を解説しているのであわせてご確認ください。
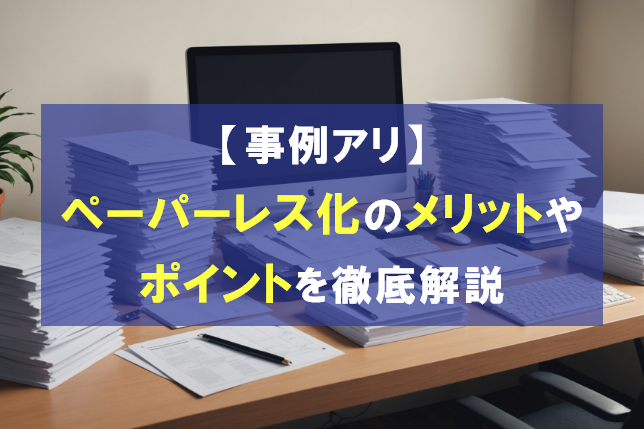
会議・コミュニケーションのオンライン化
従来は対面や書面で行っていた業務連絡や会議を、メッセージやビデオ通話、チャットツールなどオンラインに切り替える方法です。
メールやチャット、ビデオ会議ツールの導入でどこからでも協議や情報交換が可能になります。リモートワーク環境にも適しており、業務効率や従業員のワークライフバランスの向上に直接つながります。
集客・営業活動の効率化
集客・営業活動の効率化とは、これまでオフラインで行っていた商談や営業活動をデジタルへ切り替えることです。
たとえば、企業のホームページを作成すると、企業情報を発信することで集客を集めることができます。また、問い合わせフォームを設置するといつでも商談の依頼が受け取れるなどの対応が可能になり、顧客対応もスムーズになります。
さらに、営業管理ツールを活用すれば営業の進捗を社内で共有でき、案件の引き継ぎも簡単です。デジタル化によって営業担当者の負担を軽減し、効率的な集客や売上アップにつながります。
情報の一元化
情報の一元化は、社内に分散していたデータやファイル、顧客や在庫情報などを統合・一体管理できる仕組みを作ることです。クラウドシステムで文書やスケジュールを共有したり、チームタスクを可視化しやすい環境の整備を行います。
これにより、複数部門や従業員が同じ情報にアクセスでき、効率的な業務推進だけでなく、在庫や顧客内容のリアルタイム把握・分析、経営課題の明確化にも役立ちます。
情報の一元化については、以下記事で詳細を解説しているのであわせてご確認ください。
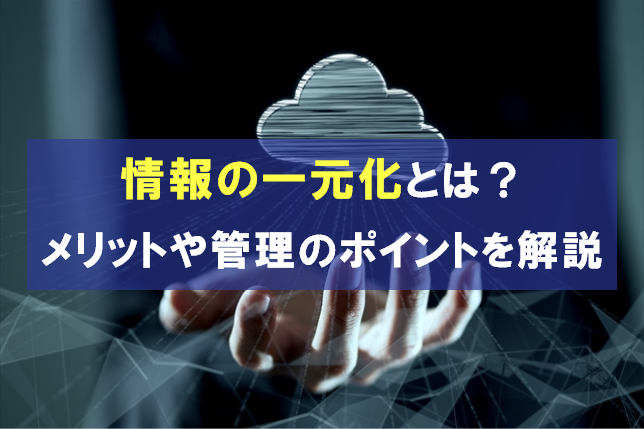
業務自動化ツール
デジタル化をさらに進めるには業務の自動化ツールが効果的です。主な例としては以下のようなものを上げられます。
- RPA(Robotic Process Automation:パソコン上の単純作業を自動化)
- MA(Marketing Automation:マーケティング業務の自動化)
- AI(人工知能:データ分析や予測に活用)
- IoT(モノのインターネット:センサーや機器からデータ収集)
このようなツールを導入することで、
- データ入力やチェック
- 在庫管理、品質チェック
- 販売調査、文書作成
- 受注、発注、勤怠、売上管理
- メール配信や顧客情報管理
など幅広い作業を自動化できます。
ツール導入による自動化で効率・生産性は大幅がアップし、ヒューマンエラー防止やコスト削減も期待できるのです。
DXツール「Hirameki 7」導入の具体例
Hirameki 7は複数機能をワンツールに提供している効率化ツールで「名刺管理」や「ファイル管理ストレージ」から「Webサイト制作」や「営業リスト検索」「メール配信」など多様な機能を提供しているため、ペーパレス対応や社内情報共有・営業管理にも適したツールです。
以下Hirameki 7を活用した具体例を3つ紹介しますので、業務改善や効率化の事例として参考にしてください。
例1.書類の電子送付とペーパレス化
社会保険労務士・行政書士北川亮事務所さま(以下北川さま)は、Hirameki 7で複雑な書類事務を効率化することができました。行政書士の事務所を運営していた北川さまは多くの書類の交換と管理に疲労感をもっておりました。
そこで北川さまが見つけたのがHirameki 7で提供している「ファイル管理」機能でした。ファイル管理のための大容量ストレージを提供しているのはもちろん、パスワード付きのファイル共有URLを発行することができ、安全に書類を共有することができるようになりました。北川さまは「書類のやり取りにかかる時間が大幅に削減され、業務効率が向上した」とお話しくださいました。
事例の詳細は「士業の導入事例 社会保険労務士・行政書士北川亮事務所様|Hirameki 7(ヒラメキセブン)」からご確認ください。
例2.名刺管理機能で営業管理を効率化
A社は営業活動の一環でメールマガジンの配信を予定しておりました。適切なツールを探していたA社は複数機能をワンツールで提供しているHirameki 7を見つけました。
「名刺管理」と「メール配信」機能がそろっていたため、CSVファイルで管理していた名刺情報をツールに登録でき、名刺上のメールアドレスにメールを一斉配信することができました。スマートフォンの撮影で名刺を登録できたため、手元の名刺管理も楽に効率化できたとのことです。
例3.ホームページ制作で顧客対応を効率化
ホームページと問い合わせフォームがなく、取引先との問い合わせ対応に悩みをもっていたB社は社内にホームページの制作が可能な人材がなく、予算も限られている状況でした。
そこでB社はHirameki 7の「Webサイト」と「フォーム」機能を活用し、ホームページを制作しました。ノーコードでかんたんにお問い合わせフォーム付きのホームページが制作でき、お問い合わせフォームから取引先の問い合わせだけでなく、求人の応募も対応できるようになりました。
デジタル化の進め方・ポイント
デジタル化を成功させるには、自社の現状にあわせて最適な段階を踏んで進めていくことがポイントです。下記のような具体的手順で、業務のデジタル化計画を進めていきましょう。
デジタル化の目標を決める
まず業務デジタル化によって達成したい目的を明確に設定します。会社ごとに業務課題や方向性が異なるため、何をどのように変えたいのか具体的な目標を立てることが大切です。
目標はできるだけ定量的な指標を設けることで、その後の効果測定や運用改善につながります。たとえば「在庫管理の手間を○年末までに半減」「収益を○%アップ」等の目標を事前に決めることで、現実的な計画を立案・推進できる環境を整えることができます。
現状の課題を整理する
次のステップは、設定した目標達成を妨げている課題や問題点の整理です。
業務現場のヒアリングや現状分析で、どこの作業で非効率やミス・無駄が発生しているかピックアップし、デジタル化の効果が大きく出る範囲や優先順位を整理します。
課題を明確化することで、具体的な改善策検討やPDCAサイクル(計画‐実行‐評価‐改善)の実行が可能になるでしょう。
業務の現行とデジタル化の優先順位を決める
課題整理が終わったら、現行業務の中でどこからデジタル化すると最も効果的か、改善のインパクトやコスト・時間を踏まえて優先順位を決めていきます。
たとえば、ヒューマンエラー発生が多く損失額が大きい箇所がある場合は、そこから順番に対応するのが有効です。売上や業務効率の改善余地が高い範囲を優先し、現実的なロードマップを作成しましょう。
デジタル化の方法・ツールを決める
優先順位が決まったら、課題ごとに必要なデジタルツールや改善方法を選定します。自社のリソース・体制・予算を十分考え、適切なITサービスやシステムを導入できる準備を進めます。たとえば在庫管理の効率化を目指す場合、物流連携できるツールや受発注の電子化システムが必要でしょう。
また、どれほど有用なデジタルツールでも自社で運用・定着できなければ意味がありません。社内のリソース・運用可能な人材を考慮し、自社に合った方法から段階的に活用をはじめることが重要です。
社内に周知・浸透させる
デジタル化を実施したら、必ず社内メンバーへ新しい手順やルールをしっかり周知し、定着させる取り組みが必要です。
最初は手順変更やツール導入の混乱もあり得るため、適切な教育や説明会を実施して活用方法を共有します。社内の理解を深めることで、取り組みがスムーズに広まり業務改革が現場まで根付くでしょう。
導入後の評価・改善を行う
デジタル化はツールやシステムを導入して終わりではありません。実際の効果や業務改善度合いは目標値でしっかりチェックし、不足や問題点が出た場合は原因を分析しPDCAを継続する必要があります。時には取り組みの見直しや新たな施策を導入するのもポイントです。
まとめ|自社に最適な方法でデジタル化を推進し競争力を高めよう
デジタル化は、業務効率化・コスト削減・新たな価値創造など、多くのメリットが期待できます。しかし自社の状況や目標を考慮せずに手当たり次第にツールやサービスを導入しても効果につながりません。現状をしっかり分析し、目的や課題に合わせ最適な方法で取り組みを進めることが、会社全体の競争力向上のカギです。
この記事で解説したポイントや具体例を参考に、ぜひ今できることから自社のデジタル化をはじめてみてください。デジタル化を起点に、新たな事業展開や価値創出にもチャレンジできる体制づくりを目指しましょう。