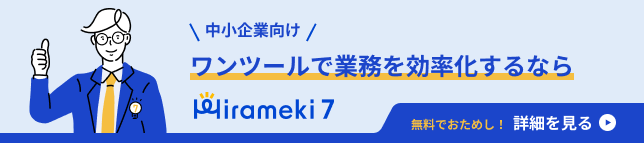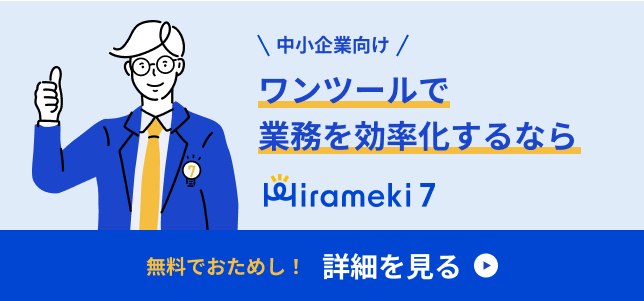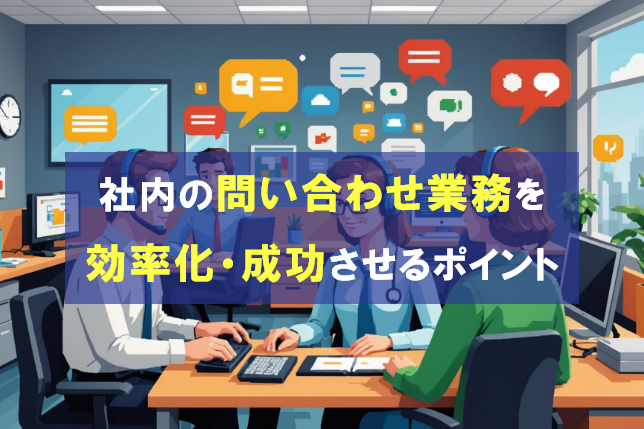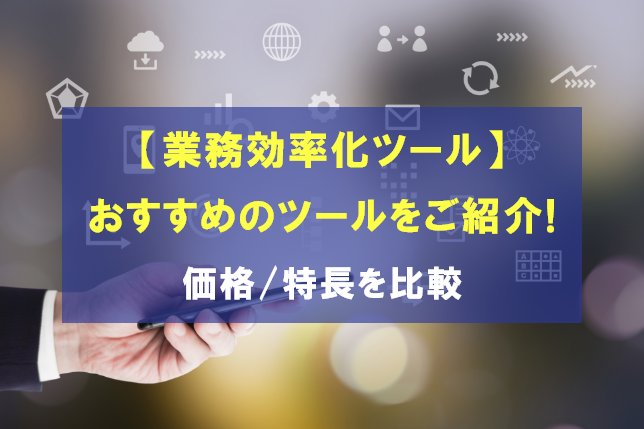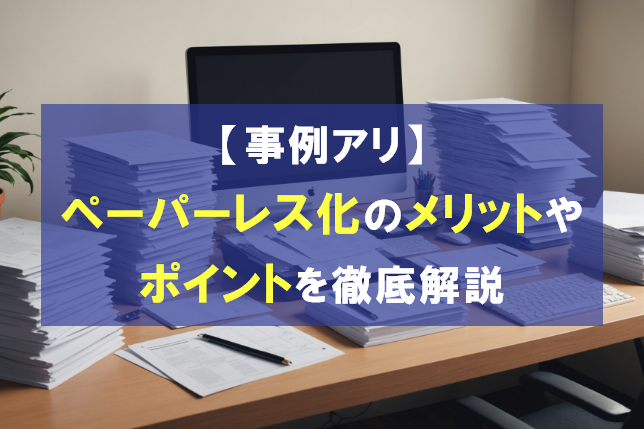
会社の書類やファイルが山積みで、管理や検索が大変と感じたことはありませんか。
ビジネス環境の変化や働き方の多様化により、紙からデータへの移行、いわゆるペーパーレス化に注目が集まっています。企業がペーパーレス化を進める理由は多く、コスト削減や作業時間の短縮、業務効率化など、さまざまなメリットが期待できます。
本記事ではペーパーレス化の基本から、電子契約やクラウド管理など可能な具体的な方法、事例までを詳しく解説しているのでぜひご確認ください。
目次
ペーパーレス化とは
ペーパーレス化は、紙を利用してきた書類や資料をデジタル化し、紙に頼らない環境を実現する取り組みです。具体的な方法として、初めから文書や資料を電子データで作成し紙を介在させないもの、紙で作成した文書を後からデータ化するものという2つのパターンが存在します。
ペーパーレス化は、企業が現状の業務フローを改善し、ビジネスの生産性を高める重要な方法です。
ペーパーレス化のメリット
ペーパーレス化によって得られるメリットは多岐にわたります。業務効率やビジネス全体の生産性向上だけでなく、コストの削減やデータ活用推進、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進の土台になる点も特筆すべきです。
くわえて、セキュリティ強化、多様な働き方の実現、企業イメージの向上といった観点からも、ペーパーレス化は現代の企業経営において重要な取り組みとなっています。これらのメリットを理解し、各企業の現状や課題にあわせて取り入れることが成功へのポイントとなるでしょう。
コスト削減
ペーパーレス化によって企業はさまざまなコストの削減が可能となります。書類や資料を紙で管理している場合、紙代・印刷代・プリンターや複合機のメンテナンス費用、文書の郵送や運搬にかかる費用、廃棄処分費用など多くのコストが発生します。これらの作業を電子化し、システムやクラウドサービスを利用することで、紙媒体そのものや印刷・搬送・保管に関わる費用が大幅に削減可能です。
また、文書をデジタルデータで保存することで、オフィス内に大量の書類を保管するスペースが不要になり、オフィスの賃料削減にもつながります。くわえて、デジタル管理なら文書検索や共有も効率化され、経理や総務などの業務工数を削減、人的コストも抑えられます。
こうしたさまざまな観点でのコスト削減は、ペーパーレス化に取り組む大きな動機となるでしょう。
業務が効率化され生産性向上に繋がる
紙の資料を用意したり、ファイルに綴じたり、請求書を封入するなど、紙を介する業務には多くの手間がかかります。ペーパーレス化を行うことで、これらの作業が不要になり、作業時間を大幅に削減可能です。
特に稟議書や申請書などの社内ワークフローも電子化されるため、担当者や承認者が出社しなくても遠隔で確認や承認作業を進められます。これにより、意思決定のスピードアップや作業の滞留防止が実現し、現状の業務全体の生産性向上が期待できるでしょう。
また、デジタル化された資料は社内外の関係者との共有も容易になり、メールやオンライン会議でもスムーズな情報伝達ができ、社内連携やグループ活動の活性化にも効果的です。業務効率の改善は、結果として企業全体の競争力向上にも貢献します。
柔軟な働き方を実現できる
ペーパーレス化が進むと、紙の資料に頼った出社や対面での業務の必要性が低下します。つまり、書類の確認や押印といった目的でオフィスへ出向く必要がなくなるため、テレワークをはじめとした多様な働き方が実現できます。
たとえば、営業職が外出先から申請や承認手続きをオンラインで行ったり、遠隔地にいる従業員がリアルタイムで資料を閲覧できる環境を整えられるなど、働き方改革と親和性の高い仕組み作りが可能です。移動時間の削減や直行直帰のしやすさなど、業務負担の軽減にもつながります。
DX推進の第一歩となる
ペーパーレス化は、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進の基盤となります。DXとは、「データやデジタル技術を通じて業務やビジネスモデルを変革し、競合優位性を確立すること」です。
企業が紙書類に頼った業務をデジタル化・電子化(ペーパーレス化)することで、
- 全体のデータ管理や業務プロセスの効率化される
- データが蓄積され、事例分析や業務改善など多様な用途でデータを活用できる
- 部門を越えた情報連携がスムーズになる
上記のようなメリットが得られ、DX推進におけるスタート地点に立つことができます。DXを推進したいものの、ハードルの高さを感じていたり、何から始めればよいかわからない企業にとって、ペーパーレス化はおすすめの第一歩です。
DX推進については、以下記事で詳細をご説明しているのであわせてご確認ください。
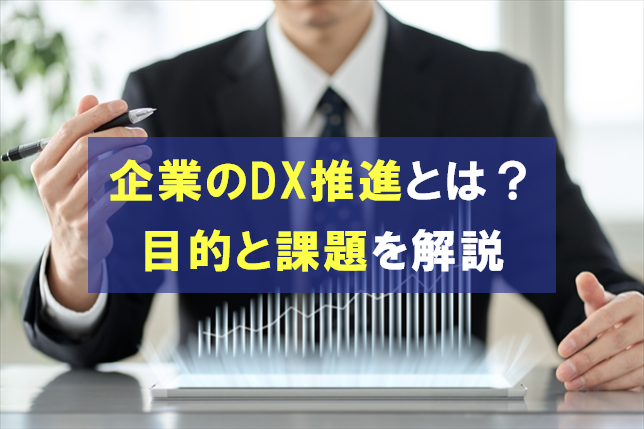
セキュリティの強化
ペーパーレス化により内部統制や情報セキュリティが大きく向上する点もメリットのひとつです。紙の資料では、物理的な鍵付きキャビネットなどの管理が不可欠ですが、それでも紛失や持ち出し、改ざんなどリスクが存在します。一方、電子化された文書は、システム上でアクセスや閲覧の権限管理が行えるため、意図しない情報流出や不正利用を防止できます。
また、データは劣化しないうえ、バックアップで復元も容易です。こうした電子化・デジタル管理によるリスクコントロールの強化は、現代企業に不可欠な取り組みといえるでしょう。内部統制の観点からもデジタル文書管理は成功事例が多数あり、安全性の高い業務環境を目指す企業におすすめです。
ペーパーレス化の例
ペーパーレス化の例として
- 申請、承認業務のデジタル化
- 文書の電子化、クラウド管理
- 電子契約の導入
- 帳票の電子化
- 勤怠管理
などが挙げられます。
申請・承認業務のデジタル化
申請書や稟議書などの申請・承認フローは、ワークフローシステムなどのツール活用でペーパーレス化が可能です。これまで紙で書類を回覧し押印してきた業務を、デジタル上で完結させることが可能です。
システムを利用することで書類の受け渡しの手間を省き、申請ミスや文書紛失を防げます。また、外出先やテレワーク中でもすぐに申請や承認ができるため、意思決定のスピードアップが図れます。
働き方や組織体制が多様化する現代において、クラウド型ワークフローシステムの導入はペーパーレス化と業務改善の両立につながる方法です。
ワークフローシステムについては、以下記事で詳細をご説明しているのであわせてご確認ください。
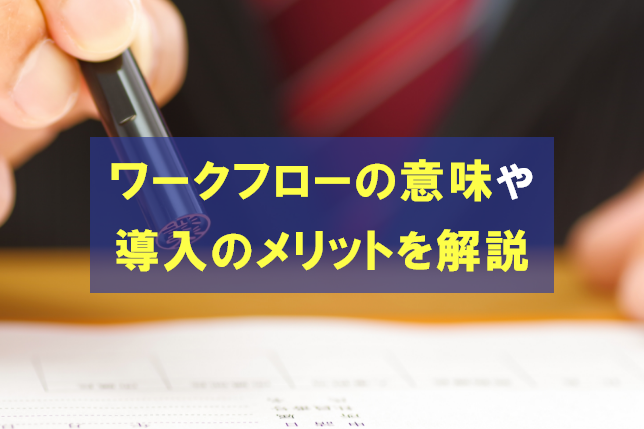
文書の電子化・クラウド管理
文書を電子化し、クラウドで管理することもペーパーレス化のひとつです。
テレワークやリモートワークの普及によって、どこからでも業務データにアクセスできる仕組みが不可欠になっています。従来の紙による資料管理では、オフィスに行かなければファイルを閲覧できず、業務のスピードや効率が制限されていました。
電子保管が可能なシステムやクラウドアプリの導入によって、社員はどこにいても必要な資料をすぐに検索・共有できるようになり、社内の情報共有と情報管理の品質が向上します。グループ・チームでの共同作業もスムーズになり、大量の紙資料を保存する保管スペースも不要になります。
クラウド管理に関しては、以下記事で詳細をご説明しているのであわせてご確認ください。
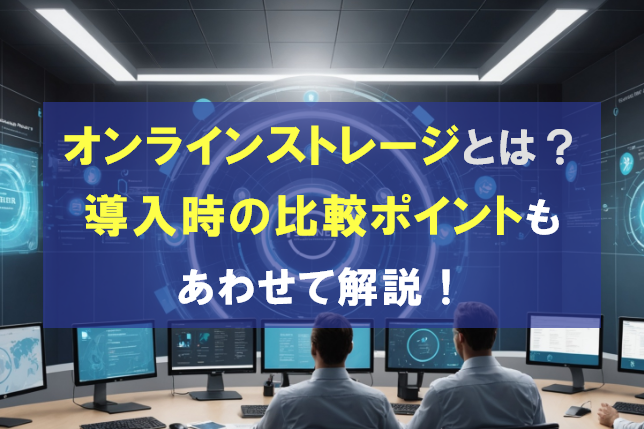
電子契約の導入
電子契約は、契約書類のペーパーレス化を実現するソリューションです。電子契約システムの導入により、契約締結のために印鑑を押す作業、書類の郵送、出社など、紙の契約に伴う作業の手間やコストを削減できます。
契約書はクラウド上で保存・管理できるため、物理的なスペースも不要です。契約内容の改ざん防止や、よりスピーディな契約締結が可能になる点も大きなメリットといえます。ペーパーレス化を進める企業にとって、電子契約の導入はビジネスの現場で実感できる効率化と安全性の向上をもたらす方法です。
帳票の電子化
インボイス制度や電子帳簿保存法の施行など、帳票の電子化ニーズは増加傾向にあり、ペーパーレス化によって印刷・発送作業の手間や紙のコストも削減できます。
また、請求書や領収書などをデータで管理することにより、保管スペースや検索の手間も軽減されます。さらに、災害や事故などのリスクにも強く、物理的な保管場所が必要ないため、情報が失われるリスクを回避できることもメリットのひとつです。
帳票管理の効率化は自社だけでなく、取引先を含めたビジネス全体の生産性向上に寄与する重要なポイントです。
勤怠管理
勤怠管理もペーパーレス化が可能です。従来の勤怠管理は紙のタイムカードや出勤簿に頼ることが多く、集計や給与計算の際にミスが発生しやすいことが課題でした。オンライン勤怠管理システムを導入することで、社員の勤務状況や打刻時刻が自動で記録・管理され、勤怠情報を迅速かつ正確に把握できます。
データをもとに時間外労働の発生状況を検討したり、集計したデータを給与ソフトと連携して効率よく給与計算を行えます。
ペーパーレス化を行う際のポイント
ペーパーレス化から得られるコスト削減や業務効率化、企業イメージ向上など多様なメリットを享受するには、いくつかのポイントを押さえて取り組むことが大切です。現状の社内業務フローや利用している紙媒体の状況を把握し、最適な方法やツールを選択する必要があります。段階的な導入や社内での周知・浸透、継続的な現場サポートなどを意識することで、ペーパーレス化の効果を最大化できるでしょう。
部分的・段階的に進める
ペーパーレス化は全社一斉に導入するのではなく、部分的・段階的に少しずつ進めることで現場への負担や混乱を防げます。
はじめからすべての紙文書をデジタル化するのは時間と手間がかかり、現場では業務が一時的に滞る懸念もあります。そのため、部署単位やプロジェクト単位、特定の業務プロセスからスモールスタートを実施するのがポイントです。
取り組みの中で発生した課題を把握し、システムや運用の改善を重ねながら徐々に導入範囲を拡大していくとよいでしょう。現場から「便利」「使いやすい」といった評価を得られれば、次の導入フェーズもスムーズに進みます。成功事例を横展開することで、全社的なペーパーレス化も実現しやすくなります。
ペーパーレス化の必要性について社内に理解してもらう
ペーパーレス化を円滑に進めるには、社内全体にその意義とメリットの周知・浸透を図ることが不可欠です。経営層から現場の従業員まで、なぜペーパーレス化に取り組むのか目的を明確にし、業務にどんな効果や変化があるのか丁寧に伝えましょう。
導入によるコスト削減やスムーズな業務運営、データ活用の利便性、時間や手間の削減など、現場の具体的な改善ポイントを解説し、全社での取り組みとして周知を徹底すると良いです。各部門が自分ゴトとして必要性を理解し、疑問や不安を解消してからプロジェクトを開始することで、変革を着実に実現できます。ペーパーレス化のメリットを把握してもらい、効果的な推進に結びつけましょう。
目的に合ったシステムやツールを導入する
ペーパーレス化の導入を進める際は、どんな文書や業務プロセスを電子化すべきか、明確な目的設定と課題の洗い出しが重要です。現場へのヒアリングを行い、自社の業務や部門ごとのニーズにマッチしたシステム・ツールを選定します。
たとえば、経理分野のペーパーレス化であれば経理システムや会計ソフト、社内書類や契約関連はワークフローシステムや電子契約サービスが適しています。タイムカードの電子化には勤怠管理システムが効果的です。
目的や業務内容ごとに最適なITツールを導入することで業務の効率化やペーパーレス化がスムーズに進みます。導入時は機能や操作性も考慮し、現場での使いやすさや運用効率を重視しましょう。
Hirameki 7でペーパーレス化した事例
次に、Hirameki 7を活用してペーパーレス化を推進し、実際に成功を収めた事例をご紹介します。Hirameki 7では、「電子文書のクラウド管理が行えるファイル管理機能」や「申請・承認業務をデジタル化できるワークフロー機能」が搭載されているDX支援プラットフォームです。
今回はファイル管理機能を活用したペーパーレス化に焦点をあてて、実施内容や解決できた課題・具体的な効果をご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
書類やりとりの時間を半分に
| 事務所名 | 社会保険労務士・行政書士北川亮事務所さま |
|---|---|
| 事業内容 | 社労相談/行政書士相談 |
| 課題に感じていた部分 | ペーパーレス化していない部分に非効率さを強く感じていた |
| Hirameki 7導入のきっかけ | ・価格面の手ごろさ・使いやすさ |
北川さまは、 顧客との書類のやりとりを電子化することで対応にかかる時間を大きく減らすことができました。体感としては、紙でやりとりしていた頃は2〜3日かかっていたものが、今では1日で完結するようになり、以前と比べて半分以上のリソースを節約できているとのことです。
▼具体的な活用方法
・書類を電子化して、ストレージ上で一元管理
・ 顧客とのやりとりには「かんたんファイル送信」機能を使って、PDF書類をスムーズに共有
上記によりリソースの削減だけではなく、「オフィス内の紙書類を大幅に削減」し、「ファイルの修正や管理もスムーズ」になったとのことです。
より詳細な事例内容については、「 導入事例 社会保険労務士・行政書士北川亮事務所」にてご確認ください。
まとめ|ペーパーレス化を推進するために大切なこと
ペーパーレス化の成功には、ITツールやシステムの導入だけでなく、メリットの周知や社内理解が欠かせません。現場での浸透を図りながら、各オフィスの状況に応じて段階的に導入を進めることが効果的です。
導入時には、誰でも利用できるシンプルな仕組み作りや社内ルールの整備も重要になります。グループウェアやワークフローシステムなど、ペーパーレス化をサポートするツールは多様化しており、導入を検討する際は業務課題や目的に合ったサービス選びも意識しましょう。