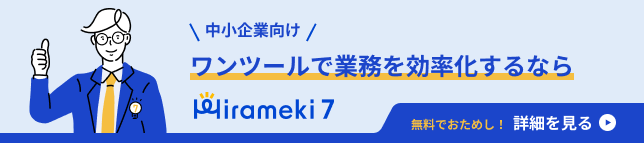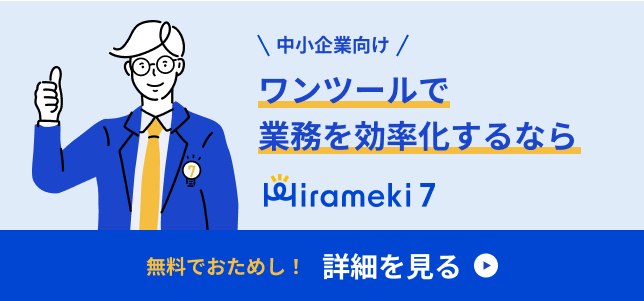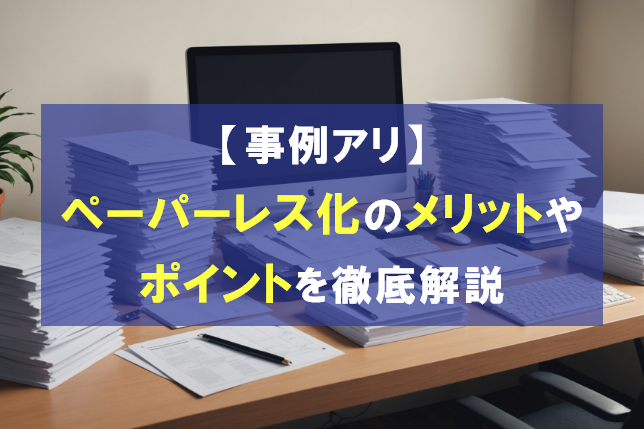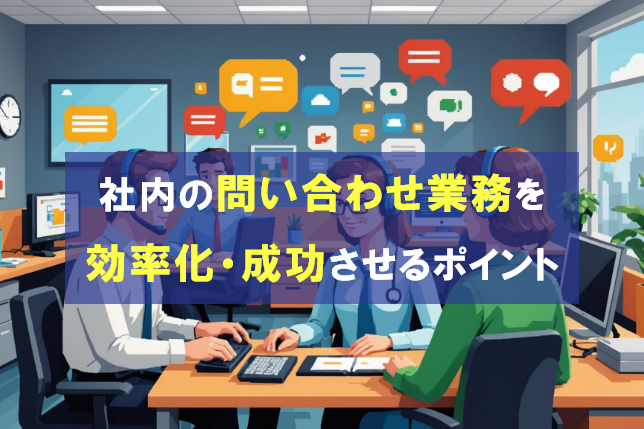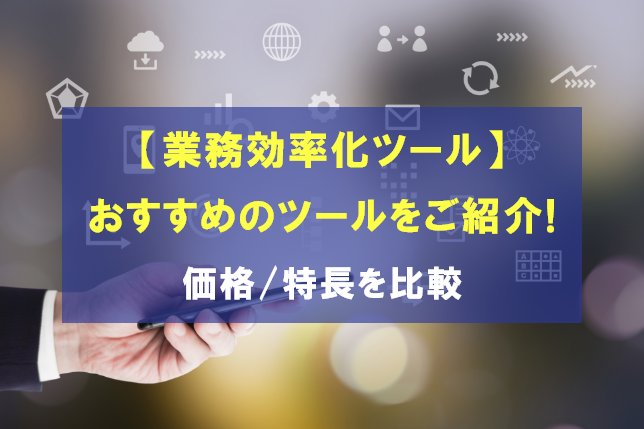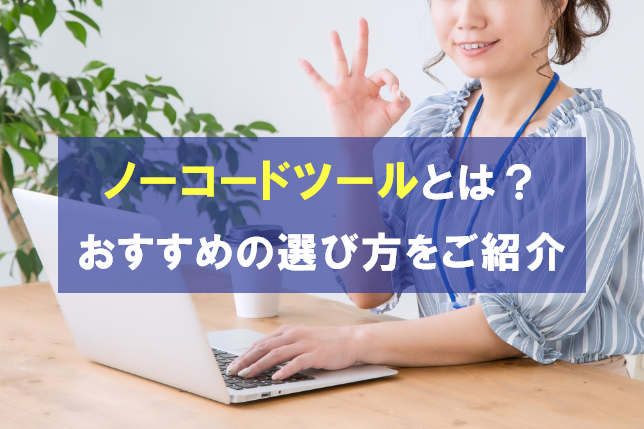
ノーコードとは、プログラミングの専門知識が不要で、多様なシステムやアプリの作成が可能な手法です。ローコードとの違いも意識しながら、より低コストに開発や運用を進めたい人に注目されています。
目次
ノーコードツールとは
ノーコード(No Code)ツールは、プログラミングの専門知識が不要で、直感的な操作でWebサイトやアプリの構築を行えるツールです。
標準で用意された機能を用いてドラッグ&ドロップの操作だけで作業できるため、専門知識が不要です。プログラミングコードを書けない人でも、社内で運用するシステムをスピーディに作成しやすく、IT部門やエンジニアを増やす余力がない場合にも役立ちます。
さらに、ノーコード技術の活用により、ユーザー自身が変更や改善を行える体制を整えやすくなるので、自社のビジネス課題や目的に合わせた内容のアプリケーションを素早く用意できます。
ノーコードとローコードの違い
ノーコードとよく比較されるローコード(Low Code)は、完全にコードを排除するのではなく、必要最低限のソースを書くだけで開発を進める手法です。
ノーコードに比べるとある程度のプログラミング知識が必要ですが、より複雑な機能や他社ツールとの連携が可能になるため、柔軟性に優れています。全面的にコードを書くフルコード(Full Code)と比べると、コード量が削減できるメリットがある点はローコードも同様です。
ノーコードとローコードはいずれも開発スピードを高める方法として注目されており、企業でのDXを推進したい場合に役立ちます。求める機能や拡張性によって使い分けることで、効率的な開発やシステム運用を目指せます。
ノーコードのメリット
ノーコード開発は、大きく以下3つのメリットがあります。
非エンジニアでも開発が可能
ノーコードツールを導入すると、コードを書かなくても機能やデザインを組み立てられます。そのため、プログラミング知識のない社員でも開発ができ、リソースの拡大や開発期間の短縮に繋げることが可能です。
開発のコストや時間を削減できる
ノーコード開発は、開発工程でプログラミングコードの記述を省略できるため、スピーディに成果物を作り上げられます。急ぎでシステム運用を開始したいときにも対応しやすく、業務アプリのアップデートが必要になった場合でも手軽に手を加えられる点がメリットです。
操作にかかる時間や外注費用を抑えることで、トータルのコストを下げられる利点があります。
イメージや要件を形にしやすい
ノーコードツールは、完成形をイメージしながらそのまま形にできるため、コンテンツのデザインや機能を直感的に組み込めます。外部の制作会社に要件定義を伝える時間やコミュニケーションの手間が軽減される点も利点です。
標準搭載の豊富なテンプレートを組み合わせるだけで、多様なデザインやレイアウトをサイトに反映しやすくなります。意図に合わない修正が発生しにくいため、企業が理想とするシステムやサイトの構築を効率的に進められます。
ノーコードのデメリット
ノーコードには自由度や拡張性に一定の制限があり、標準機能の範囲内でしかカスタマイズできない傾向があります。以下の点に注意して、ノーコードでの開発が適切かを確認するようにしましょう。
プラットフォームへの依存度が高い
ノーコードツールで作成したアプリやWebサイトは、特定のプラットフォーム上で動作するため、移行や大規模な変更をする際には制約を受けやすいです。
また、別のツールに乗り換える場合、既存のデザインや機能をそのまま引き継げず、再びゼロから構築し直さなければならないケースもあります。プラットフォーム自身のアップデートやサポートポリシーによって仕様が変わることもあり、思わぬコストや作業時間がかかる可能性があります。
一部のノーコードツールはプログラミングコードの出力やAPI連携に対応していますが、完全に自社に合わせたカスタマイズを行うには追加の実装が必要です。将来的な拡張や安定運用のためにも、ツール選定時には長期的な視点でプラットフォームの信頼性を見極めることが求められます。
カスタマイズや拡張性に制限がある
ノーコードツールは、定型化された機能やデザインパーツを組み合わせていく開発方法のため、独自の仕様を細かく反映する作業には向きません。複雑なサーバーサイドの処理や特殊な機能を必要とする場合、ノーコードツールだけでは対応不可能なこともあります。
自由度を高めたいなら、ある程度のコード記述を挟めるローコードツールやフルコードの利用も検討する必要があります。ツールの提供範囲を事前に確認することが重要です。
大規模開発には向かないケースがある
ノーコードツールは、あらかじめ用意されたテンプレートやパーツを活用してシステムを構築するため、大規模開発で求められるような複雑な機能の実装は苦手です。1つ1つの機能を自由に拡張していくには限界があり、大規模な業務システムを作る場合にはフルコードやローコードのほうが安定するケースがあります。
求める要件が大きいほど、ノーコードのメリットよりも制約のほうが目立つようになるため、現場の要望や長期的な成長を考慮した検討が必要です。用途が比較的小規模であればノーコードで十分ですが、大きな組織のコアシステム等を作りたい場合は、別の方法を視野に入れておくと安心です。
ノーコードツールのタイプ
ノーコードツールは、サービスごとに得意分野や特徴が異なります。自社の目的にあわせて使えるパーツや機能が揃っているかどうかが重要です。
プロダクト開発
一つ目は、Webアプリやネイティブアプリなどのプロダクト開発に特化したノーコードツールです。ツールによっては顧客に向けたプロダクト開発だけではなく、後述するWebサイトの制作や社内業務の効率化など、さまざまな業務をまとめて行えるものもあり、汎用性が高いです。
他タイプに比べて、さまざまな目的に対応した機能が揃っているため、自社の導入目的にあった機能・コスト感かどうかを確認するようにしましょう。
社内の業務改善を目的としたアプリ
次に、顧客管理や在庫管理、案件管理など、社内の業務を改善することを目的にアプリを作成するツールがあります。データベースを構築して複数のツールを連携させたり、既存のエクセルデータを活用したりできる機能を備えたものを選ぶと便利です。
もしDXが遅れていたり、社内に点在する業務ツールの統合が進んでいなかったりする場合は、プラグインやAPIなどの拡張機能が豊富なものが役立ちます。エクセルのような既存データがある場合は、それを基に効率的にアプリ開発を進められるタイプを選ぶと、業務プロセスの改善をスピーディに実現できます。運用のしやすさやユーザー管理の手軽さも見極めて導入しましょう。
Webサイトの制作
ノーコードツールはWebサイトの制作にも活用できます。LP(ランディングページ)から企業サイトまで、豊富なテンプレートがあらかじめ用意されているため、美しいデザインを短期間で作成可能です。ドラッグ&ドロップの操作で要素を配置できるうえ、コーディング知識が不要なので、初心者でも直感的に編集しやすい特徴があります。
また、情報発信を行う際に、制作会社を挟んでいる場合は都度コストがかかるケースが多いですが、ノーコードであれば低コストかつスピーディにサイトを構築して運用できる点が魅力です。専門のエンジニアを雇わなくても、自社スタッフで更新作業などを行えるので、プロモーションやサービス紹介の効果を高めやすくなります。
Hirameki 7では、月額800円(税別)からノーコードでWebサイトの制作が可能です。また後述する、HTMLメールの制作・配信機能に加え、ノーコード以外の業務改善に便利な機能が多数そろっています。無料のトライアル期間も設けているので、ノーコードツールを試してみたい方は、ぜひお申し込みください。
ECサイトの構築
ECサイトの構築に特化したノーコードツールは、オンラインでの販売に必要なカートや在庫管理、決済といった機能を標準で搭載しています。
プロジェクトの初期費用や作業時間を抑えるメリットもあり、プログラミングコードを書かずにECサイトを実現できます。システム連携にも対応しているノーコードツールなら、外部のデータやアプリとも連携しやすくなり、多くの商品を効率よく管理することが可能です。ECサイト構築を検討している場合は、機能面の比較やセキュリティ対策をしっかり確認することが重要です。
HTMLメールの制作
HTMLメールの制作にもノーコードツールを活用すれば、ドラッグ&ドロップを中心とした簡単な操作でデザインを構築できます。コーディングが苦手な担当者でも、配色やレイアウト、画像の挿入などをカスタマイズしながら作成できる点が利点です。
ツールによってはテンプレートも充実しているため、主旨に合ったメールを短時間で作れることも魅力といえます。特別なプログラミングの知識がなくても、マーケティング施策に沿ったHTMLメールを送信して顧客に配信しやすくなるでしょう。
ツールによって対応している送信形式(ステップメールや条件配信)が異なるため、あわせて確認するようにしましょう。
ノーコードツールの選び方
ノーコードツールを選ぶ際は、以下の観点から自社にあったツールを選択するようにしましょう。
利用目的や用途に沿って選ぶ
ノーコードツールには、前述したとおり、ECサイト特化型やWebサイト制作向け、業務アプリケーション専用など、さまざまな種類があります。どれほど多機能なツールでも、自社の用途に合わなければ導入のメリットは薄れます。
求める運用形態に合致するかどうかや、不要な機能が多すぎないかなどをよく検討するようにしましょう。
例えば、ECサイト構築が目的であれば、商品登録や決済機能を搭載しているツールが必須です。業務アプリ開発を予定している場合は、データ管理や社内連携に強い機能を持つツールを比較すると判断しやすくなります。
要件を満たす機能が揃っているかどうかを確認し、運用の流れをイメージしやすいノーコードツールを選びましょう。
費用対効果が良いツールを選ぶ
ノーコードツールは無料プランや低コストで提供される製品もあるため、一見すると導入のハードルが低い印象を受けます。しかし、サポート体制が薄かったり、必要な機能が不足していたりすると、実運用で手戻りが増えて結果的にコストがかさむ場合があります。
逆に料金の高いツールだからといって、すべての機能が自社にとって有益とは限りません。目的に合った機能を的確に搭載し、短い学習期間で使いこなせるかどうかが費用対効果に直結します。導入時のトレーニングや運用サポートも含めて検討し、自社の目標を果たせるツールを選ぶことが大切です。
サポート体制やマニュアルが整っているツールを選ぶ
ノーコードツールを活用するには、使い方が分からなくなったり、トラブルが生じたりした際のサポートが欠かせません。サポートデスクが日本語対応しているか、マニュアルが分かりやすく充実しているかなどをチェックしましょう。
ノーコードツールを提供している企業の多くは海外拠点の場合があるため、問い合わせに英語力が必要となるケースもあります。日常的な運用で問題が起きたときに迅速なサポートが得られないと、作業が滞る原因になりかねません。快適にシステムを管理し続けるためにも、サポート体制やマニュアルの整備状況を事前に調べることが大切です。
操作性が良いツールを選ぶ
ノーコードツールは、実際に操作してみると使い勝手が大きく異なることがあります。複雑なUIではかえって時間がかかるため、誰が使っても分かりやすいデザインになっているか確認することが大切です。
必要なデバイスでのプレビューや編集がスムーズに行えるか、ドラッグ&ドロップ操作に対応しているかなどを確かめましょう。操作性の良いツールを選ぶことで、プロジェクトを円滑に進められます。
適切なノーコードツールを導入し業務改善を
ノーコードツールはプロダクト開発や、サイト制作、社内の業務改善などさまざまな場面で活用できます。
導入を検討している方は、目的・料金プラン(費用対効果)・対応デバイス・サポート体制などを比較しながら最適なノーコードツールを探してみてください。